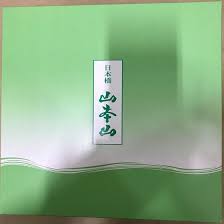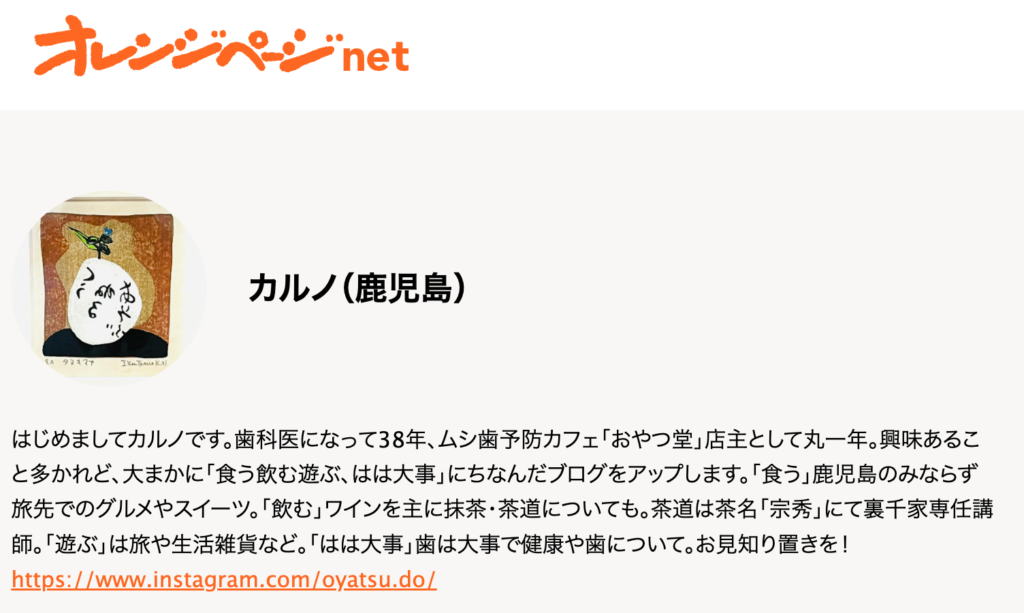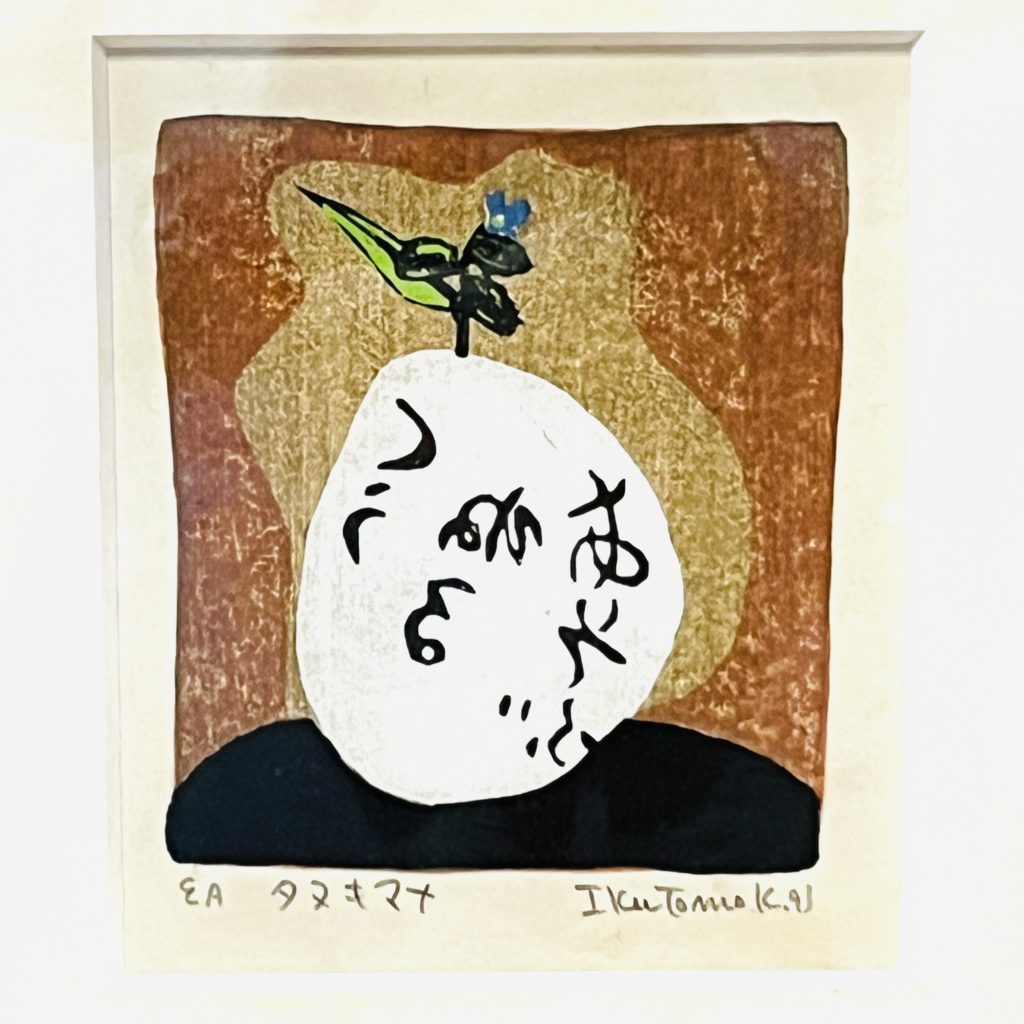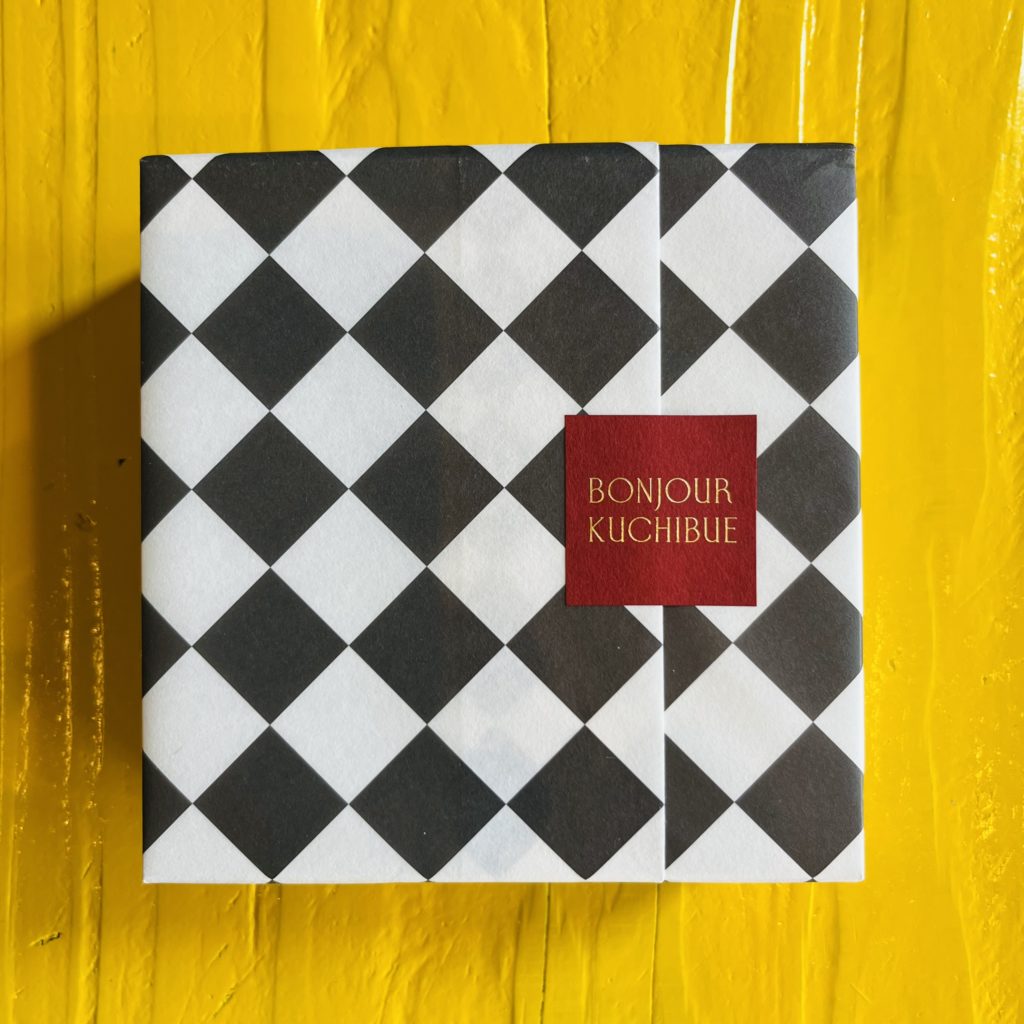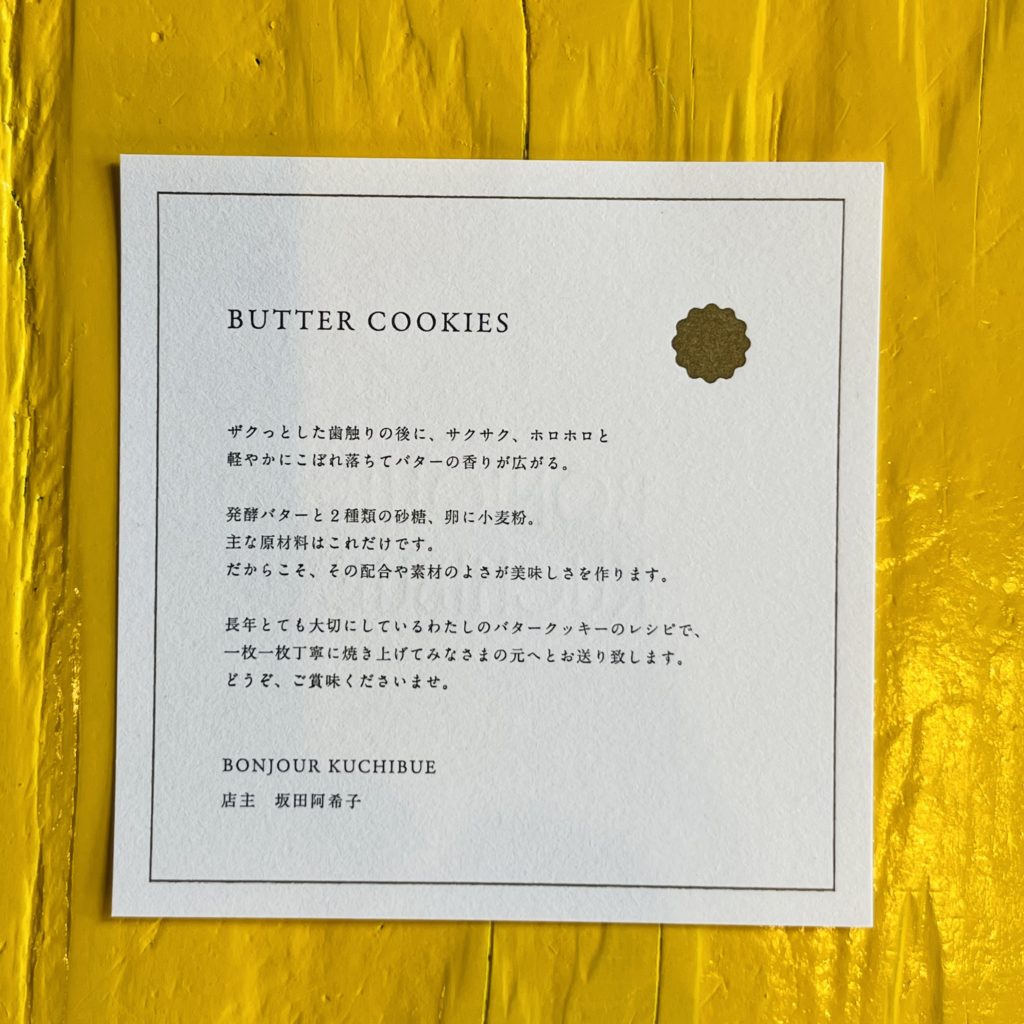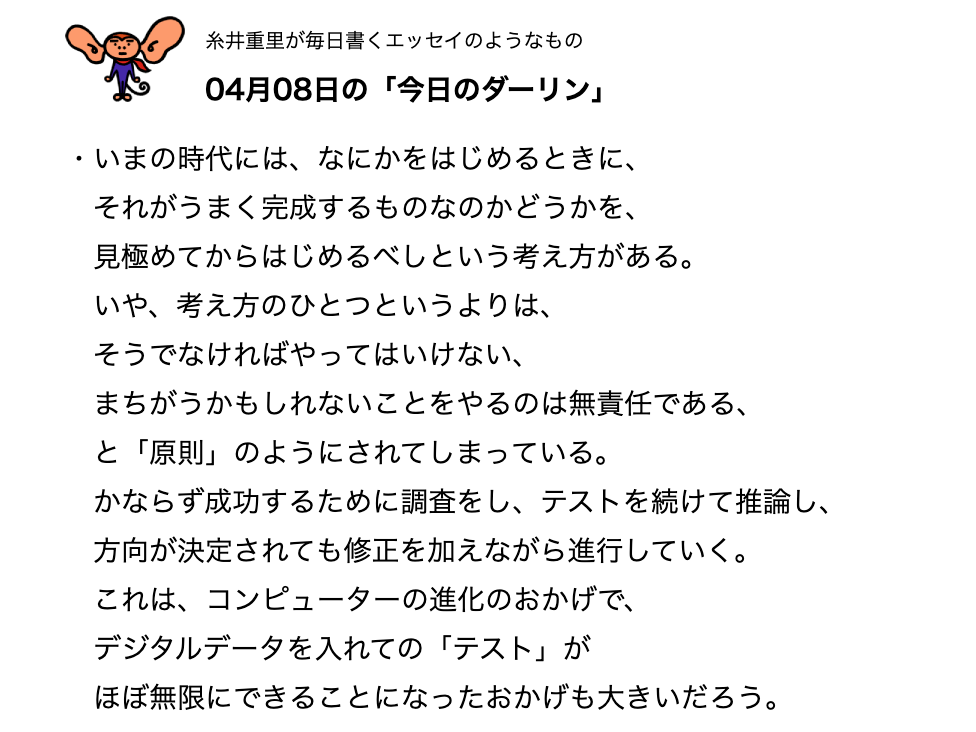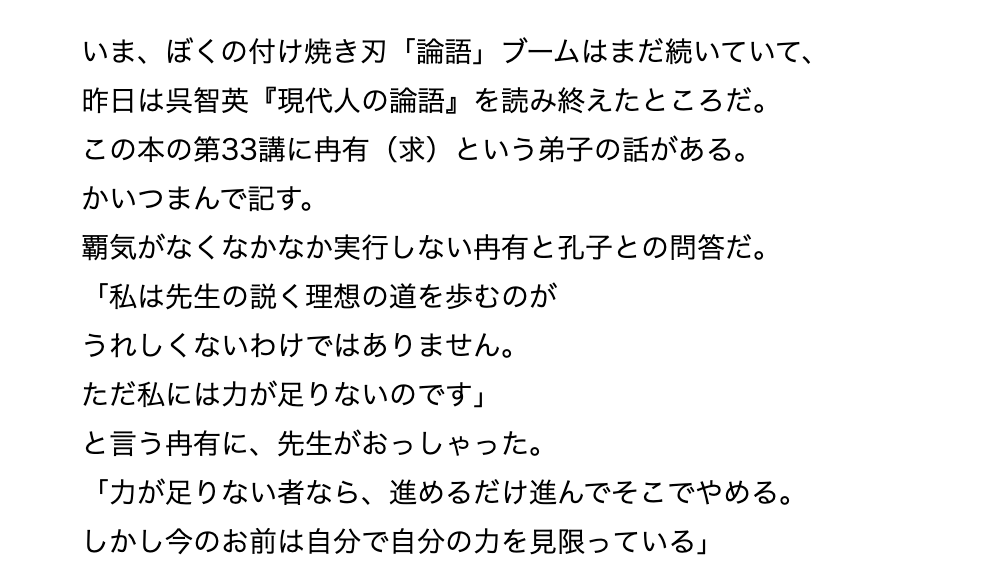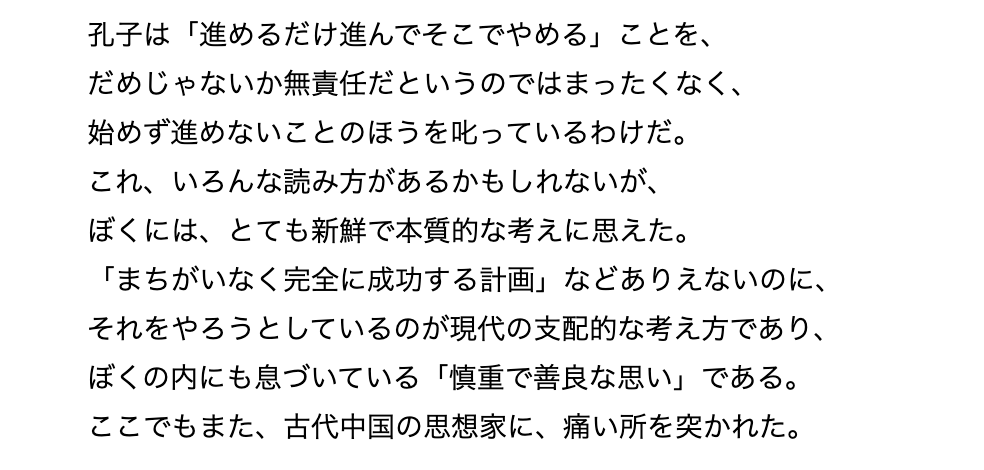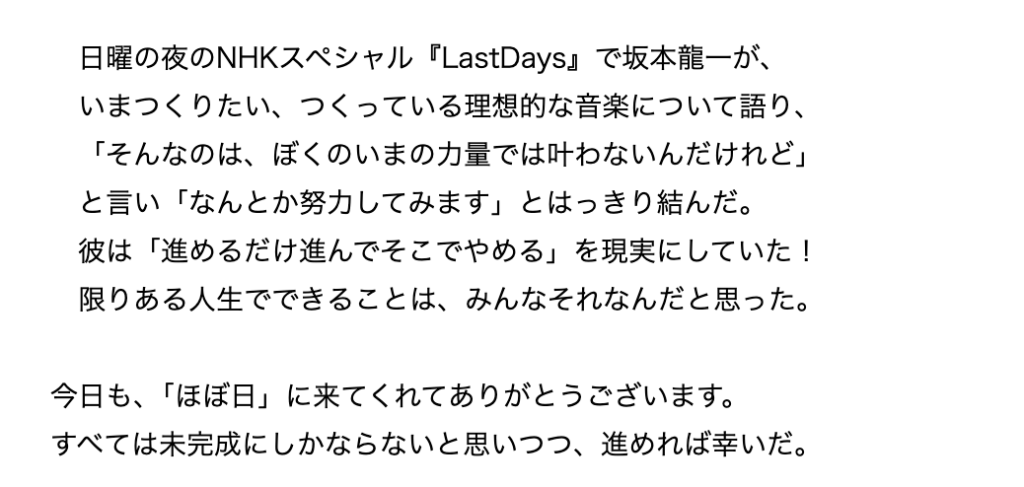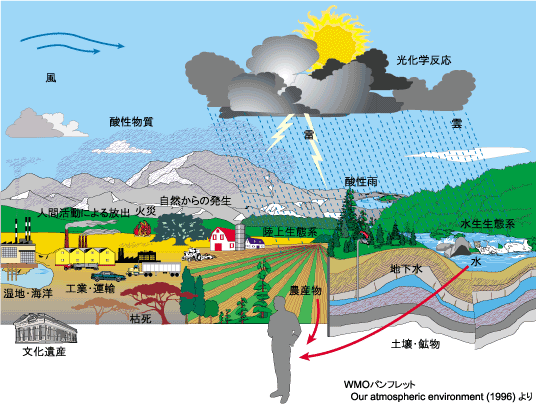「花柘榴生きるヒントの二つ三つ」森 慎一
2024/05/25投稿 5/31加筆 6/4追加解説 は『こころが瞬間にぶつかって句が成る。よくあることなのだろうか。人事句でありながら、花石榴(はなざくろ)の実が一樹にぽつりぽつりとあるのを、永年見つづけてきた人の句。花はたくさん咲くが、実は少ない。やはり、二つ三つ。『風のしっぽ』所収』(引用元 )。解説を読んで混乱するのは柘榴の花と実の時期です。花柘榴 (柘榴の花)は初夏五月から七月、実は十月から十一月です。今回はセミナーのネタとして「生きるヒント=健康に老いる」について。
訪問診療に行き始めていろいろな気付きがあります。当たり前ですが、最後まで食べられます。コミニュケーションが取れなくなっても、ご家族のことがわからなくなっても、食事されます。食べるということは「口腔ケア」が必要になります。・・・先日ラジオを聴いていて合点しました。
ラジオ登場は「澤田誠:さわだまこと 」氏。引用元 )。
2)使わない記憶は劣化していく!・・去る者は日々に疎し引用元 )。引用元 )。引用元 )。
3)思い出は美しすぎて!(記憶違いは必然)引用元 )。上下ひと揃いの服を上下バラバラ(ジャケットとパンツ(ズボン)にわける)にしまうようなことです。では、なぜこのようにするのか?引用元 )。引用元 )。
4)隠れ脳梗塞引用元 )。引用元 )。
5)認知予備能とは引用元 )。引用元 )。
6)意思ではなく記憶が将来を決める!引用元 )。引用元 )。引用元 )。道程 」には『僕の後ろに道は出来る』とありますが、後ろに出来た道を踏まえて、これからの「道」「人生のゴール」を歩むのです。
「脳」は生存維持装置であって、本来は記憶装置ではないと理解してください。脳もひとつの臓器、体に良い事は脳にも良いのです。健康的な生活(食事・睡眠・運動)が健康な脳を維持します。良質の睡眠について一言。歩くことと早寝早起きの習慣化で良質の睡眠を得ることができます。詳しくはこちら「BBTime 651 リズム 」をご覧ください。では皆様、ご自愛の程ご歯愛の程。
VIDEO
VIDEO
VIDEO
追加:六月四日は何の日?かつて「むし歯予防デー」で、今では「歯と口の健康週間 」となってます。始まりは1928年(昭和3年)。実はこの年に始まったもうひとつの健康づくりに関することが・・「ラジオ体操 」なんです。こちら を。
この絵本の原作者「長谷川和夫」氏登場のラジオ番組見つけました。6/11午前2時まで視聴可能です)。6/14は認知症予防の日 、ドイツ人医師アロイス・アルツハイマー の誕生日にちなんで。
ラジオはこちら! ジャンプ先、上から三番目、是非お聴きください。